下二段活用造句
- ウィクショナリーに下二段活用の項目があります。
- 下二段活用をすることがある。
- 口語の下一段活用は、すべて文語の下二段活用に由来している。
- 古語?一部方言では上二段?下二段活用も母音が交替する(語幹母音の交替)。
- 古典文法では、「萌え」は、ヤ行下二段活用の動詞である「萌える(萌ゆ)」の連用形である。
- 下二段活用(しもにだんかつよう)とは、日本語の主に文語文法における動詞の活用のひとつである。
- 受け身?尊敬?自発?可能の「れる」「られる」を博多弁では「るう」「らるう」と言い、下二段活用する。
- 現代語では上一段活用、下一段活用になってしまった動詞が上二段活用、下二段活用で使われることがある。
- 母音語幹動詞はいわゆる上一段活用?下一段活用?上二段活用?下二段活用であり、語幹が/i/か/e/で終わるものとして分析される。
- これらの語はすべて語幹が1音節であり、他の1音節で終わる下二段活用やラ行四段活用と同音になるのを避けるために語幹を安定化させたものと考えられる。
- 用下二段活用造句挺难的,這是一个万能造句的方法
- この時期には、「読む」から「読むる」(=読むことができる)が、「持つ」から「持つる」(=持つことができる)が作られるなど、四段活用の動詞を元にして、可能を表す下二段活用の動詞が作られ始めた。
- なお下二段活用には「得(う)」「寝(ぬ)」「経(ふ)」という1音節の語が存在するが、学校文法ではウ?エ段音からを活用語尾、その前でを語幹とするため、これらの語は「語幹がない」あるいは「語幹と語尾の区別がない」というように説明される。
- 九州方言の主な特徴は下二段活用をすること、状況可能を 未然形+「らるる」と、能力可能を 連用形+「きる」といい分けること、共通語で連用形+「ている」という所を、習慣や現在移動、変化している動きを表す場合、動詞の連用形+「よる」、動作の結果を表すとき動詞の連用形+「ておる」と使い分ける(アスペクトの区別)ことなどである。
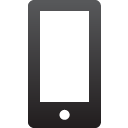 手机版
手机版